- 会員限定
- 2017/11/24 掲載
スタートアップが大失敗する3つのパターン
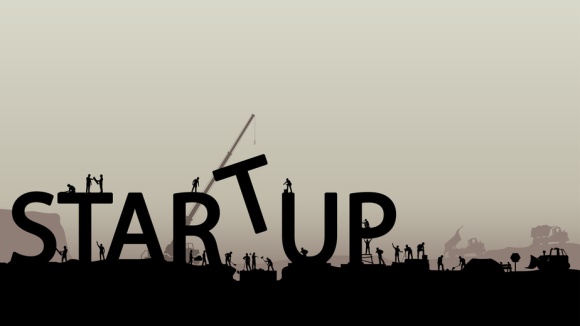
「ベンチャー企業」の陳腐化
スタートアップは、技術、インフラ、法規制、固定観念など、さまざまな要因によって解決の道が閉ざされている社会課題を創造的な方法で解決し、その解決プロセスをビジネスとして成立させる。
ユニコーン企業と呼ばれる企業は、これに加えて「大きなマーケットでビジネスを展開する/し得る」という要件を満たしている。
彼らが「幻の一角獣」と呼ばれるのは、矛盾する前者の要件(未解決の社会課題の解決)と後者の要件(大きなマーケットでのビジネス展開)を満たしているからなのである。
マーケットがあるということは、すでに経済活動が行われていて、ある程度課題が発見されている可能性が高いということだ。さらに、そのマーケットが大きいなら、マーケットが成熟している可能性も高い。マーケットが成熟している場合、既に誰かが参入障壁を築き上げてしまっていることが多い。
思い返すと、2006年1月にライブドアが証券取引法違反容疑で強制捜査を受けた、いわゆる「ライブドアショック」以前は、「起業」「ベンチャー」という言葉が大流行しており、今の「スタートアップ」的な意味合いを持っていた。
それがいつしか、「ベンチャーのコモディティ化」が起きるようになった。週末起業、1円登記、お手軽脱サラ、主婦の自宅サロン開業、そうしたものも「起業」である。普通の中堅・小規模企業が「ベンチャー」を自称することも増えた。
一方、DeNAのような「巨大化した新興企業」が、「永遠のベンチャー」とのキャッチフレーズを使うこともある。日本人は、こういうロマンにあふれる世界観が好きな民族なのかもしれない。
「ユニコーン企業」への失望
もちろん、世の中にはフェイスブック、グーグル、アップルに追随するような「世の中にインパクトを起こす起業」もあり、それを目指す人々もいる。その区別のために確立されたのが、「スタートアップ」という言葉だ。「スタートアップ」という言葉も早晩陳腐化する運命からは逃れられない。「わたしはスタートアップである」という宣言は、いつしかの「ベンチャー」と同じく、誰が使っても許されているからだ。
そこで最近登場したのが「ユニコーン企業」という名称である。これは、自称が許されないので、多少は賞味期限の長い言葉になるかもしれない。
おそらく「ユニコーン企業」という名称を空虚にする仕掛け人は、ベンチャーキャピタル界隈の人々になるはずだ。「あれもユニコーン」「これもユニコーン」と期待をあおり、それが失望に変わるという体験を生み出し、「ユニコーン」という言葉への期待値自体を消失させてしまうというシナリオである。
スタートアップが大コケする3つのパターン
「ベンチャー」「スタートアップ」「ユニコーン」と、さまざまに呼び名が変遷してきたその内実とは、「すでに確立されたビジネスモデルの枠内での新規創業」か、「大きな社会的なインパクトをもたらす新たなビジネスモデルの発明」かという区別だ。後者を目指して多くの挑戦がなされるも、なかなかうまくいかないというのが現実である。あらゆるスタートアップのサクセスストーリーは、創業者の「個人的な体験」がきっかけである。ふとしたことで広告ビジネスの新たな形の可能性に気づく。創業者が直面した社会課題の解決を目指したら、それがビッグ・ビジネスになった…。成功したスタートアップの社史は、そんな話で一杯だ。それが自分にも起きる可能性を、あらゆる起業家が持つものである。しかし同時に、それが「勘違い」である可能性も考慮しておく必要がある。そして、ほとんどのスタートアップは後者なのである。ではなぜ失敗するのか。典型的な3つの失敗パターンを見ていこう。
【次ページ】スタートアップが大コケする3つのパターン
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR



