- 会員限定
- 2017/07/14 掲載
セコム発展の裏には「戦いの原則」に沿った「創造的破壊」があった(2/2)
セコムに見る経営者の「戦いの原則」応用術
各種戦闘要素を企業の人材、事業・サービス、資金、技術、企業風土などの経営資源に置き換えてみると、「集中発揮セシムル」の意味がよく理解できます。いかなる組織・個人であれ、新規事業を始めるとき、「兵力節用の原則」にのっとって、旧事業を整理、縮小または廃止しなければなりません。とはいえ、このことは「言うは易く、行うは難い」というのが実情です。
集中および兵力節用の2つの原則を一体として行うことを、象徴的に表現しているのが「創造的破壊」です。創造的破壊はスクラップ・アンド・ビルドと同意義です。人間の習性として、ビルドには賛成するものの、スクラップには多くの抵抗があることは、みなさんもよくご存じのとおりです。
日本で警備業をゼロから立ち上げたセコムは、本年で創業55周年を迎えますが、創業後間もない時期に、今日の基盤を築いた創造的破壊を地で行く決断をしています。私は陸上自衛隊を退官後、約7年間セコムの研修部で社員教育に従事し、セコムの空気を若干吸っています。
ビジネス・事業は熾烈な戦いです。実際の戦争と異なり、人を殺傷する残虐性や物を破壊する暴力性はありませんが、企業の存続と従業員の生活をかけた厳しい戦いです。戦いに勝利しなければ企業の明日はないといっても過言ではありません。
創業以来のセコムの軌跡をたどると、事業に対する考え方、折々の決断などが「戦いの原則」に見事に合致していることに気付かされます。「集中」および「兵力節用」の2つの原則を一体として行った創造的破壊の具体例を1つ紹介します。
セコムは「創造的破壊」で売上の8割を占めるサービスを捨てた
セコムは、創業2年目の1964(昭和39)年にSPアラーム(日本初のオンライン・セキュリティシステム)の開発に着手し、4年目の1966(昭和41)年に販売を開始しました。とはいえ、その結果は散々でした。1966(昭和41)年度13契約、1967(昭和42)年度59契約、1968(昭和43)年度165契約です。1969(昭和44)年度からようやく伸び始めて1400契約となり、普及の目途が立ったのです。そしてセコムは、1970(昭和45)年、事業の主体を巡回警備から機械警備へと大転換しました。
「巡回警備は廃止する。常駐警備も増やさず、大幅に値上げする。今後の営業はSPアラーム一本で行く」(支社長会議における創業者・飯田 亮氏の決断)
当時、主力サービスの巡回警備は契約数が4000件を超え、売上32億円の約80%を占めていました。この主力サービスを捨てるという決断です。
その背景には、「機械でやれることは機械で」という人間尊重のヒューマニズムと、機械警備システムが将来のネットワークへと発展するという予感があったのですが、まさにスクラップ・アンド・ビルドの創造的破壊でした。
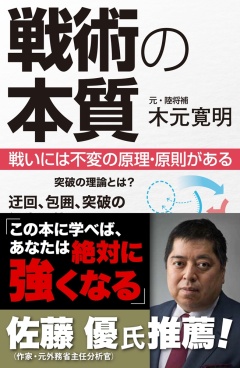
1972(昭和47)年度に巡回警備とオンライン・セキュリティサービスの売上比が50対50になり、1974(昭和49)年度には20対80に逆転しました。「もしも」の世界ですが、巡回警備と機械警備の二兎を追っていたならば、今日のセコムの発展はなかったでしょう。
1970(昭和45)年、箱根富士屋ホテルにおける支社長会議での決断は「巡回警備を廃止する」というスクラップと、「SPアラーム一本で行く」というビルドの抱き合わせでした。まさに「集中の原則」と「兵力節用の原則」を絵に描いたような、鮮やかな「創造的破壊」です。
決勝点に戦力を集中することはさほど難しいことではありません。リーダーは第二義的正面のリスクをはっきりと認め、時にはこれを捨てる非情さが求められるのです。
関連コンテンツ
PR
PR
PR


