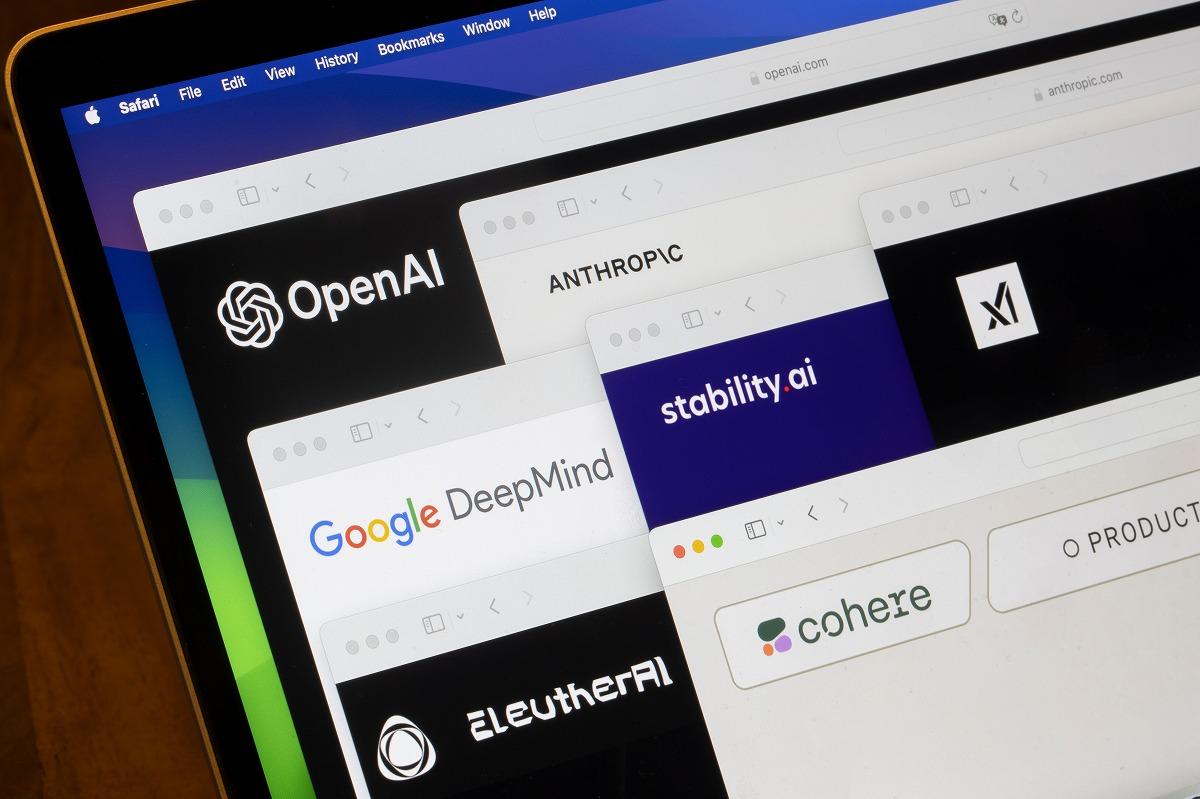- 会員限定
- 2025/04/14 掲載
【チェックリスト付】なぜ生成AI導入は「失敗」ばかり? 絶対確認すべき「12の原因」
個人と会社、生成AIで生み出せる「効果の違い」
個人から会社で利用するために必要な「どんな準備が必要か?」「安全性をどう確保するか?」「広く利用してもらうには?」などの課題を解決していきます。なぜ個人だけでなく、会社全体での利用を目標にするのでしょうか。個人と会社を比較すると、ChatGPTによって生み出せる成果は大きく異なります。
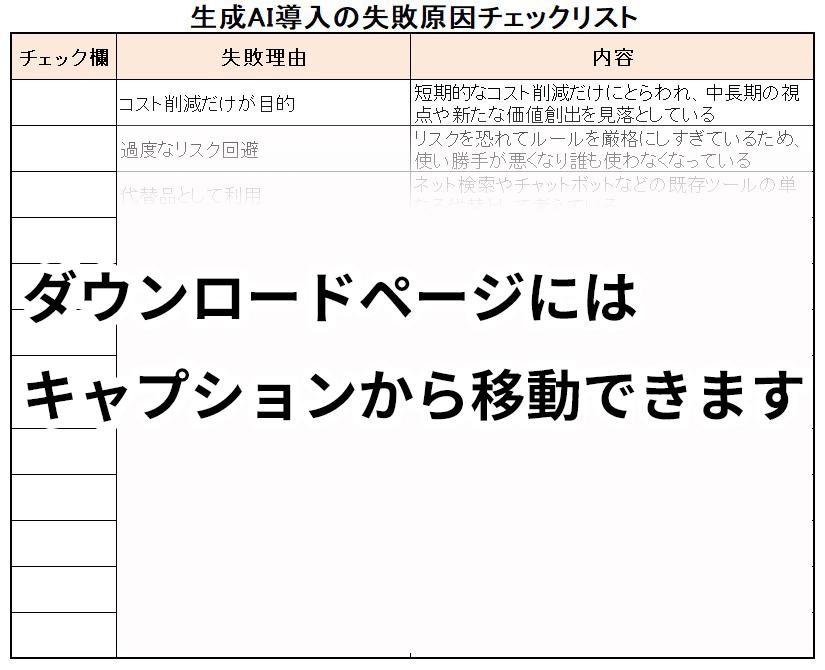
たとえば1人1日5分間の時間短縮によって、1年間なら20時間の成果となります。これが1万人の会社ならば、年間で20万時間の短縮となり、大きな成果です。
さらに売上増、生産性向上、新規事業の立ち上げ、コスト削減、業務の抜本的な改革などにおいて、個人とは比較にならない成果を期待できます。
企業が「生成AI利用」を進めるワケ
導入活用を推進するもう1つの理由として、データ活用とノウハウの継承が挙げられます。ChatGPTが持つ情報は事前に学習済みデータであり、特定の企業が持つ固有の問題には対応できません。しかし社内規則やノウハウのデータを追加で学習させれば、自社が行う特定業務への対応や、ベテラン従業員のノウハウなどをChatGPTが習得できます。こうしてChatGPTに人間が持っている能力にデータを掛け合わせることで、より大きな成果と他社との差別化も実現できます。
会社にはさまざまな部門、職種、働く場所があります。職種や部門を考慮すれば、営業や広報や人事ではそれぞれに抱える課題も異なります。また、工場や店舗や屋外の現場で働く従業員にとっては、パソコンよりもスマホでChatGPTを使える方が便利でしょう。それぞれの立場や目的や状況に合わせて、最適なChatGPTの導入活用を実現してください。
生成AI導入が「失敗する12の原因」
ChatGPTの導入が進む一方で、失敗するプロジェクトもあります。導入の検討を行う前に失敗につながる要因を把握しておけば、そうした失敗は事前に回避できます。ChatGPTで想定される失敗パターンについて、紹介します。・コスト削減だけが目的
ChatGPTに限らずITツールの導入目的として、コスト削減が強調されがちです。しかし表面的かつ短期的なコスト削減を目指すと、視野が狭くなります。たとえば人件費などのコスト削減に成功しても、一方で導入にかかる教育や社内政治などの見えないコストが増えることもあります。導入に際しては中長期的な視点も考慮しましょう。また、コスト削減という「守り」だけでなく、新たな収益を産み出す「攻め」の用途も検討してください。
・過度なリスク回避
ChatGPTには、情報漏えいや間違いなどの懸念があります。こうしたリスクを過度に恐れて、ルールやセキュリティ対策を厳重にしすぎると、使い勝手が悪くなって誰も利用しません。適切なセキュリティ対策とリスク管理のバランスを取りましょう。 【次ページ】もう10の失敗原因
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR