- 会員限定
- 2017/02/14 掲載
「古い体質」の日経が、日経電子版アプリを内製化・アジャイル開発した理由と裏側
【前編】
1月12日と13日に行われたスクラムのイベント「Regional SCRUM GATHERING Tokyo 2017」では、同社でモバイルアプリケーションの開発チームを担当する武市大志が登壇。内製化やアジャイル開発を実現するために改革と改善を繰り返してきた背景と事情を詳しく解説してくれました。
本記事はその講演内容をダイジェストで紹介します。
日経電子版 穴の空いたバケツ開発
日本経済新聞の武市と申します。日本経済新聞社のデジタル編成局の編成部にいて、スマホのネイティブアプリなどを開発しているモバイルアプリチームのリーダーをしています。
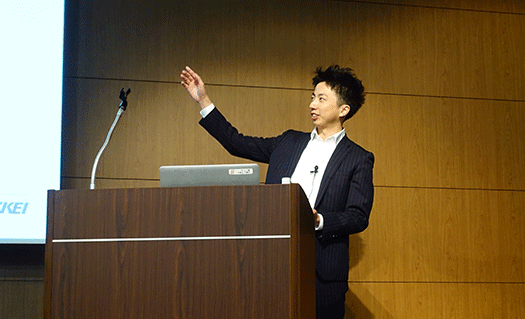
日本経済新聞って140年の歴史があります。というとカッコイイですが、古い体質の会社です。そうした中でアジャイル開発を進めている、進めようとしている現場の話をさせていただきます。
今回の話は内製化にフォーカスしていますが、決して外注や受託開発を否定する話ではありませんので、その点はご了承ください。
今日お話しする日経電子版は2010年3月に創刊されまして、有料会員は約50万人います。無料会員が300万人くらい、Webの月間アクセスが2500万人くらいです。
毎日約900本の記事を配信しています。
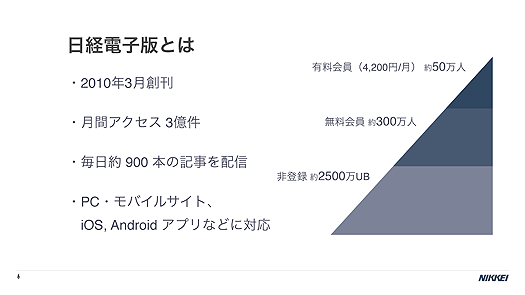
プロダクトとしては、PC用のWebサイトがあって、スマホのWebがあって、スマホのアプリがあります。私が担当しているのが、スマホ系のプロダクトになります。今日メインでお話しするのは(赤線で囲んだ)この電子版アプリです。

「穴の空いたバケツ」とは、スマートフォンのアプリのこと
「穴のあいたバケツ」というのは、コンサルティングをしていただいている深津さんの言葉です。日経電子版アプリの開発というのは、要するに穴の空いたバケツにたくさん水を貯めましょうということに似ています。

穴の空いたバケツにたくさん水を貯めようとすると、いくつか方法があります。
まず、蛇口を太くして流入量を増やす。プロモーションをするとか、SEOをするとかですね。
バケツを大きくする。コンテンツを増やすとか、無料開放などでユーザーを増やすなど。
バケツの穴をふさぐ。これはリテンション、プロダクトを日々改善して辞めていくユーザーを少なくする。グロースハックなどですね。
蛇口を太くする、バケツを大きくする、穴をふさぐ、この3つがありますが、実行する順番も大事です。例えば、蛇口を全開にしてもバケツが小さければだめだし、バケツが大きくても穴が空いたままでは水が貯まりません。
蛇口をひねる前にバケツを大きくしなければなりませんし、穴もふさがないとね、ということになります。
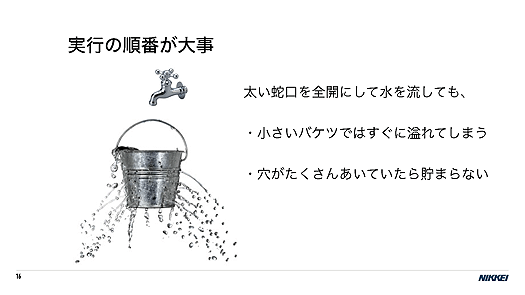
今日は3つのお話をしたいと思っています。
そもそもイケてるバケツを作るチームをどう作ったか。内製化の話です。
それから、バケツを大きくするためにやったこと。日経電子版アプリのリニューアルの話。
そしてバケツの穴をふさぐためにやったこと。グロースハックというか、リテンションの話をさせていただこうと思います。
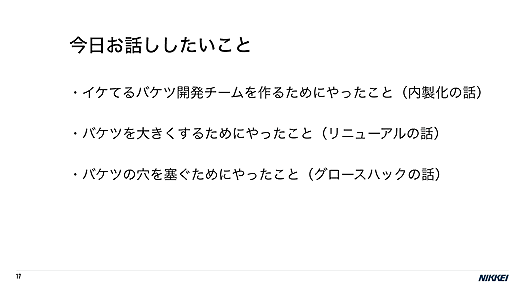
なぜ日経電子版の開発は内製化へ舵を切ったのか?
まず、イケてるバケツを作るチームを作る話から。これまで日経電子版アプリはほぼ外注で作っていました。しかしこれはスピード感が遅く、いちいち大きなプロジェクトになるんです。
例えばこれは当時の機能追加をしたアプリのビフォーとアフターなのですが、このシェアボタンを追加するのに2週間かかりましたと。
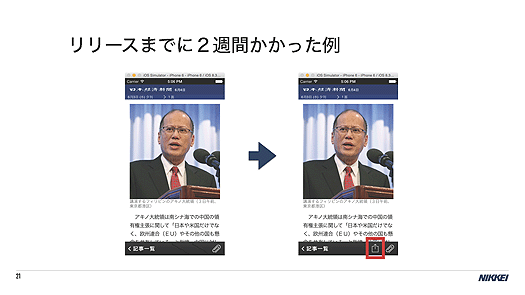
なんで2週間もかかったかというと、リリースまでにやることがいっぱいあるんですね。まず仕様を作るために要件定義書などのドキュメントを作り、それをもとに社内説明会などをして回って調整して、オッケーが出たら外部の開発会社と打ち合わせて見積書を作ってもらい、それを基に発注書を作って、テストケースを作ってエクセルでばーっと書いて。
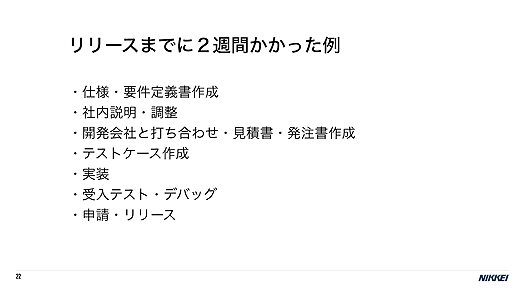
いよいよ実装しますと、じゃあ受け入れテストしますと。オッケーなら、アップルに申請を出しますと。当時のアップルは審査に1週間くらいかかっていたので、実質的にはユーザーの手もとにあの小さなシェアボタンが新機能として届くまでに3週間くらいかかるわけです。
そんなことをしていると、ボタンを作ってみたけど、位置はこっちの方がいいんじゃないかと思っても、もう方向転換するのにめちゃくちゃ時間がかかるわけです。
ボタンをひとつ追加するだけでもビッグプロジェクトになっているので、素早く提供してフィードバックを得る、といったことができませんし、実装するに当たっていろいろ壁にぶつかったりしたときにも、乗り越えたときのノウハウが外注さんには残るけれど僕らには残らない。そういうデメリットもあります。
イケてるバケツを作るには、もっと短いサイクルでのリリースで、アジャイル開発だと。
そして競合の登場や環境の変化にはもっと柔軟に対応したいし、取引コスト、つまりいちいち見積もりや発注を行うなどの手間も小さくしたい。
これらを実現するにはどうしたらいいかというと、内製化しよう、ということになりました。
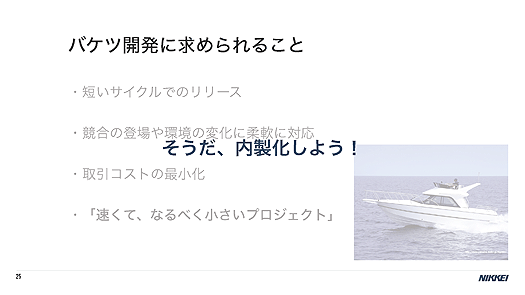
【次ページ】 メンバーは自分事としてプロダクトのことを考えられる人
関連コンテンツ
PR
PR
PR


