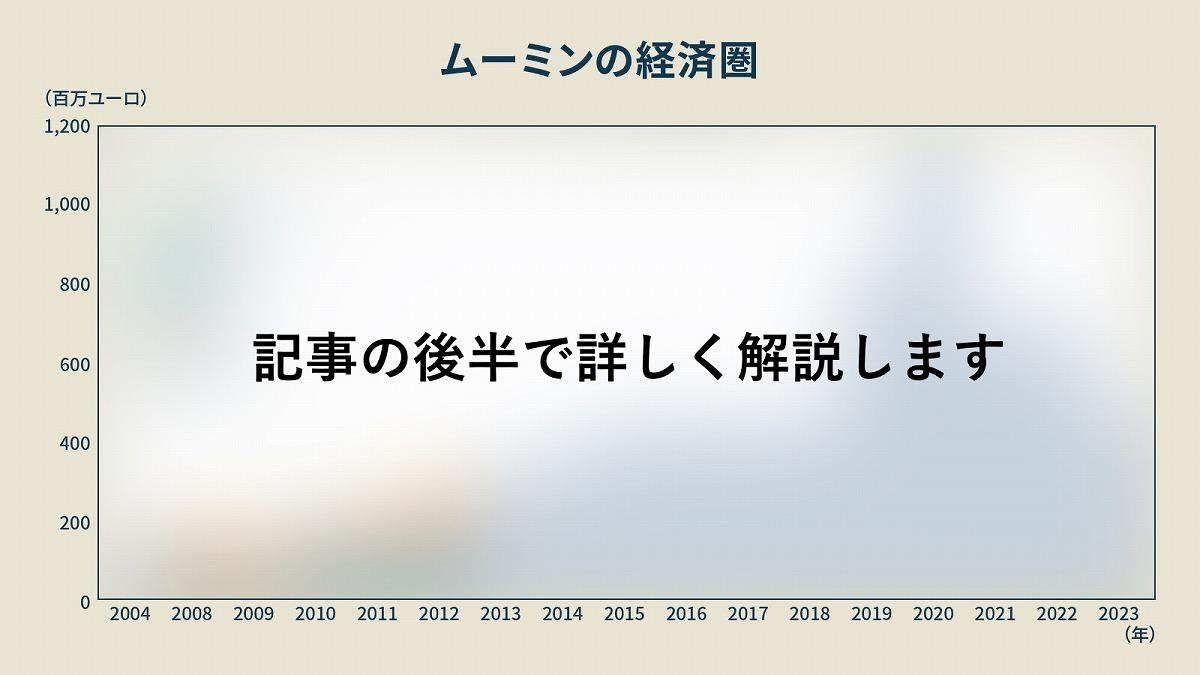- 会員限定
- 2025/02/18 掲載
生誕80周年『ムーミン』の“稼ぐ力”が結構すごい理由、知られざる…版権の実力とは?
連載:キャラクター経済圏~永続するコンテンツはどう誕生するのか(第28回)
ムーミンのヒットのはじまり
本作が広がり始めるのは、小説第3作『たのしいムーミン一家』(1948年)が1950年にイギリスで出版され、その後、1954年にロンドンの夕刊紙「イブニング・ニュース」での連載漫画が始まる頃からだ(注1)。また、1949年には自身で脚本・演出を手掛ける舞台劇『ムーミントロールと彗星』が上演され、テレビシリーズとしても実写に近いものが1959年に西ドイツで放送されている(注2)。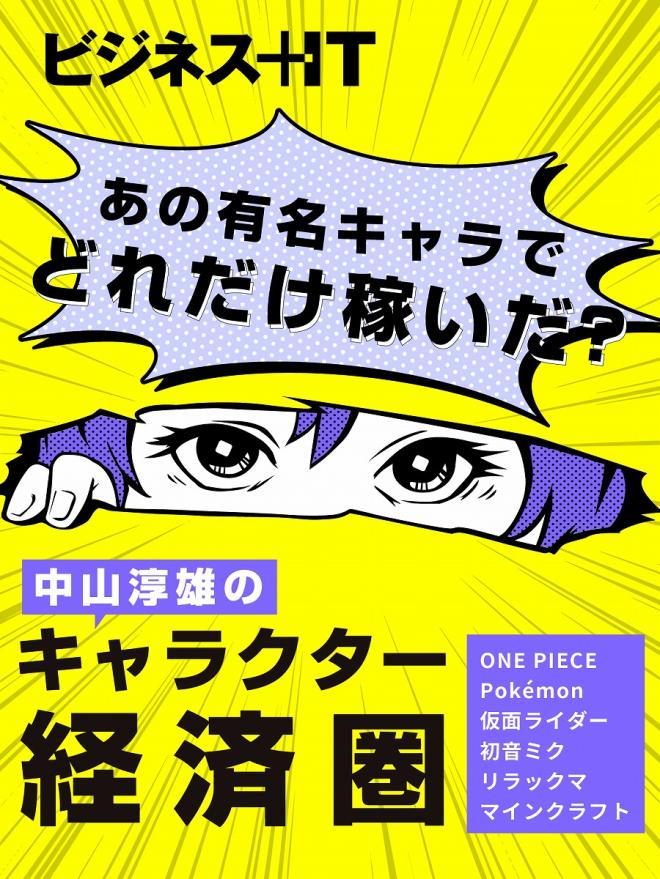
当時のTCJは、テレビCM制作の一環で社内にアニメ製作部門を持っており、『鉄人28号』で成功していた。営業部門の高橋氏は、半澤麗子氏という女性スタッフが持っていた洋書『FINN FAMILY MOOMINTROLL』に目をつける。
日本にはない奇妙なキャラクターに惹かれ、イラストレーターの一色弘安氏に色を付けてくれと依頼。一色氏は、渡されたムーミンの絵を見て、「これは面白いアニメになる」と予感したという。そこから初のアニメ化に向け交渉が進められることになる(注3)。
ムーミンのアニメ化を実現させた“ある日本人の交渉”
日本では1963年の『鉄腕アトム』をはじめ、『ジャングル大帝』『リボンの騎士』『どろろ』など虫プロがアニメ業界をけん引してきた。続くのが『狼少年ケン』『魔法使いサリー』の東映動画(現:東映アニメーション)と『鉄人28号』『宇宙少年ソラン』『サスケ』のTCJ、この3社などを中心にテレビアニメが継続された黎明の時代。そうした“子供向けSF・アクションアニメ”が中心の時代に「フィンランド作家の絵本・マンガ」というまったく別ジャンルの企画が始まるのは、1にも2にもTCJ高橋氏個人の思いによるところが大きかったのかもしれない。
当時、高橋氏はムーミンの日本語版の絵本が講談社から出ていることを突き止め(1965年に初めて日本語訳の絵本輸入、講談社によって5~6冊の本が翻訳されている状態だった)、ノーアポで講談社に駆け込む。担当編集者に聞くと、「版権交渉はエージェンシーを通して行っており、出版権のみでアニメ化などの2次使用の権利はない」ということが分かり、それを受け、ムーミンの試作絵とともにトーベ氏に直接手紙を送り、アニメ化に向けて交渉を始めたという(注3)。
トーベ氏自身はその提案に前向きだったが、海外出張などTCJから許可が下りるはずもない時代。どうしようかと思案していた折、ちょうどTCJが1969年にアニメ部門を独立させるにあたり(これが現在のADK傘下のエイケン)、高橋氏は退職してアニメ企画会社「瑞鷹エンタープライズ」(現、瑞鷹:ずいよう)を立ち上げる(注3)。
高橋氏は、その時のTCJの退職金を全額旅費につぎ込んだという。自腹でスウェーデンまでたどり着き、フィンランドからきたトーベ氏と落ち合う。通訳を入れ、たどたどしく契約書をとりかわし、「外国人作家作品の初の日本テレビアニメ作品」がはじまるのだ(注3)。
原作から「キャラデザインの改変」で激変した作品事情
アニメ化を進めるにあたり、原作ムーミンは全員が同じ造形で、キャラ同士の区別がつかないことから、大塚康夫氏(『ルパン三世』などの作画監督・キャラクターデザイン)によって、ムーミンのパパにはシルクハット、ママにはエプロンを付けるなど、原作の挿絵に登場したものを参考に、描き分けることにした(注3)。
今すぐビジネス+IT会員に
ご登録ください。
すべて無料!今日から使える、
仕事に役立つ情報満載!
-
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
-
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
-
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
-
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR