- 会員限定
- 2018/09/26 掲載
システム運用の“嬉しくない”ことをなくすNoOpsとは何か? その実現方法を解説
NoOps Meetup Tokyo #1
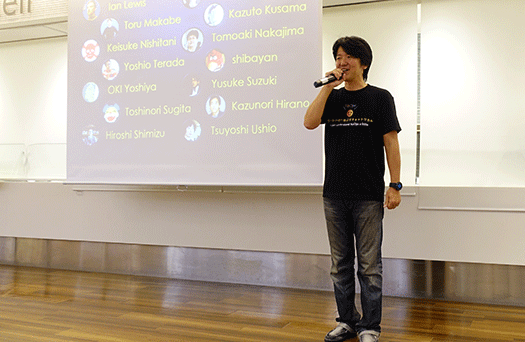
NoOpsの目指すもの
今日お伝えしたいことは3つです。「NoOpsの目指すもの」「なぜいまNoOpsなのか」「NoOpsのつくりかた」
「NoOps」とは、「No Uncomfortable Ops」つまりシステム運用の嬉しくないことをなくそう、ということ。
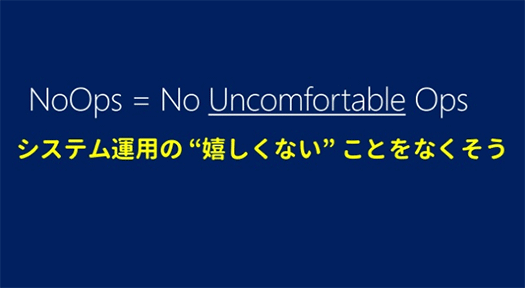
嬉しくないこととは、おもに3つあげられます。
1つ目はユーザーの体験を妨げないということ。例えば障害時のダウン、計画停止、負荷集中時の性能低下などはユーザーの体験を妨げます。
2つ目は運用保守の現場での「トイル」です。トイルとは、リリース手続きやパッチの適用など、人間がやるべきでないような作業、これを最小化しましょうと。
3つ目はシステム運用保守におけるリソースとコスト。これは忘れられがちですが、実は1つ目や2つ目はサーバリソースにお金をかけたりヒューマンリソースを豊富に投入すれば問題にならないかもしれません。でもそうではなく、リソースやコストの最適化をしましょうと。
いまならすべてが改善できる、という時が来た
こうしたことを目指したNoOpsのためにOpsを改善しようとすると、ジレンマが立ちはだかります。利用者の体験を向上させようと24時間365日運用、負荷が集中しても安定して稼働し、可用性も高めようとすると、運用の現場の負担は増し、コストもかかる。
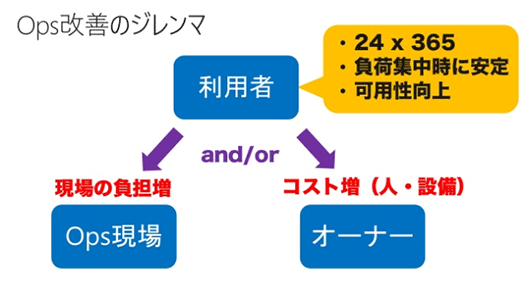
一方、運用の現場の負担を軽減しようとして、例えば待機人員をなくすとするとサービスが落ちても対応できなくなってサービスの低下につながります。また現場の負担を軽減するための設備投資やツールの導入、アウトソースの採用などはコストがかかります。
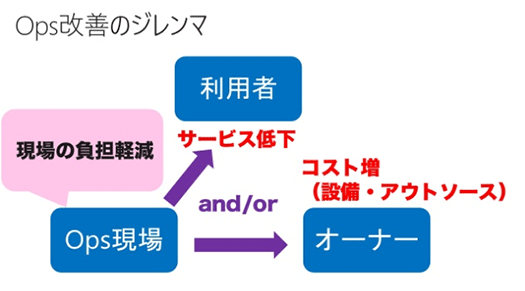
サービスのオーナーはコスト削減しようとすると、サービスの低下や運用の現場の負担増につながります。
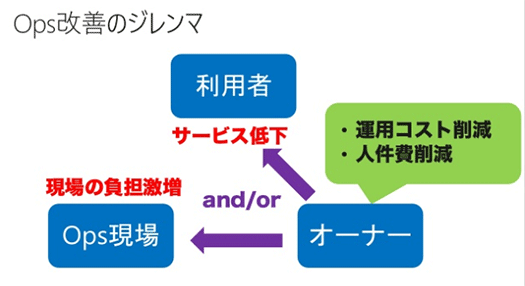
こうして「結局何をやってもあまり効果がでないね」というループになって、これまで同じようなやり方で運用の現場を何年も回してきたんじゃないかと思います。
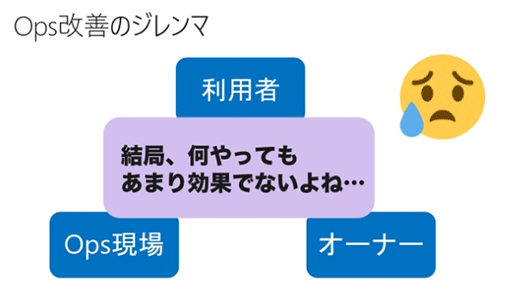
しかしいまなら、すべてが同時に改善できる、という時が来たと思っています。
(それがNoOpsへの取り組みです)
【次ページ】 NoOpsの鍵、作り方、実現するチームとは
関連コンテンツ
PR
PR
PR


