- 会員限定
- 2015/01/08 掲載
慶応大 磯辺剛彦 教授に聞く、大企業でもベンチャーでもない中堅企業の勝利の方程式
中堅企業の戦い方は、日本が生き残っていくためのヒントになる
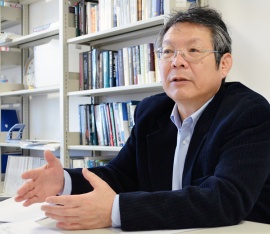
大学院経営管理研究科
教授
経営学博士
磯辺 剛彦 氏
私が中堅企業に関心を持った理由は大きく2つあります。まず1つめはネガティブな理由、消去法によるものです。日本では有望なベンチャー企業がなかなか出てこない、その対極に位置する大企業も海外で勝つのが難しい、残されたのが中堅企業だった、ということです。
私は10年ほどベンチャー企業の国際比較研究を行っています。これまで100の国や地域の起業家精神についてデータを集めているのですが、日本は何と100地域中100位。これは衝撃的な数字です。国の産業構造を変えるようなベンチャー企業が、今の日本では生まれにくいのが実状です。
それならばグローバルクラスの大規模企業でと考えた時、たとえば自動車は国外で大健闘していますが、それ以外の産業の多くは海外の大企業に歯が立ちません。
社会人類学者で東大名誉教授の中根千枝先生が指摘されていますが、日本企業が規模を拡大しようとする時のやり方は「長屋型」で、本社の下に事業部や関連会社がズラッと並ぶというものです。たとえば売り上げが数兆円の重工業企業であっても、結局は中堅中小企業の寄せ集めで、いわば「足し算」での成長です。
これに対して海外企業の拡大の仕方は、たとえば、インフラ、ヘルスケア、情報通信といった、大きな専門領域があり、その周りに必要な機能を持つ会社を衛星のように配置していく「鉄筋型」です。蜘蛛の巣を大きくしていくようなやり方で、こちらは「足し算」というよりも「かけ算」の成長が可能になります。両者が競争すると、圧倒的に後者のほうが強い。
つまり日本人特有の経営論や方法論は、ベンチャー企業にも、大企業にも向いていないということです。
一方、プラスの理由は、中堅企業の経営方法が日本人に向いていることにあります。
日本には、小さくても特定の分野で世界に負けないメーカーは非常に多い。特定の技術や製品で、世界ナンバーワンだという企業がたくさんあります。この中堅企業の戦い方が、日本企業が生き残っていくためのヒントになります。
ちなみに中堅企業研究会では中堅企業のレンジを年商10億~1000億円に設定していますが、これは中堅企業をグローバルに比較検討する時に各国で定義が違うと、正しい比較ができません。そこで意図的にこの範囲で決めておくことで後々の研究がしやすくなります。また、実体としてもこのレンジに入ってくる企業が一番多いですね。
欧米の経済的ロジックは、日本の「社会的正当性」にはそぐわない
──今グローバル比較というお話が出ましたが、欧米と日本とでは何が違っているのでしょうか。米国における企業成長の考え方はただひとつ、「小が成功すると中になり、中が成功すると大になる」というものです。つまり企業の成功は直線になっていて、成功とは成長して大きくなることです。理論ありき、データありき、実証ありきの経済的論理で、議論をしても絶対にぶれない。欧米企業はこの経済的ロジックをグローバルに展開するのです。
まず1980年代に主流となった戦略論は、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授による競争戦略論です。企業の収益性は、活動する産業領域やその中におけるポジショニングといった外部要因によって決まる、というものです。要は自社の一番魅力的な場所はどこかを考えるということですね。
1990年代に入ると、ジェイ・バーニー教授などによる経営資源に基づいた戦略理論(Resource-based View of the Firm:RBV)が注目を集めるようになります。これが現在でも主流で、企業の持つリソース、たとえばブランドや技術、ノウハウなどが競争力の源泉になるとするものです。
この2つの戦略論は、まさに経済的合理性が理論の根本になっていて、損得勘定がすべての意思決定の判断基準になります。
しかし日本の中堅企業の事例を調べてると、彼らの成功の考え方は、どうも小から大への連続ではないようだというのが我々の仮説です。創業者や経営者の思いや自分たちの使命といった経営理念が企業経営の中核になっています。お客さまに喜ばれるか、世の中からみて適正なことかといった「社会的正当性」が意思決定の基準なのです。
また人と人との付き合い方や社会構造なども、日本と欧米とでは異なっています。勉強したつもりで米国の戦略論をむやみに使うと、思いがけない副作用が起こってしまうことがあります。自分たちの仕事のやり方や心地よさ、価値観などにぴったり当てはまるやり方を採らなければ、失敗してしまう恐れがあります。戦略論やマネジメント理論なども、本来欧米とは違って当たり前なのです。
【次ページ】日本の中堅企業は海外に出なくていい
関連コンテンツ
PR
PR
PR


