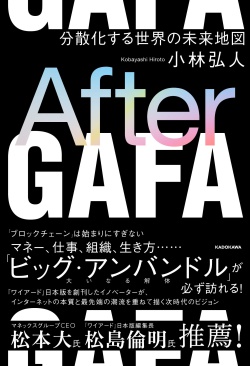- 会員限定
- 2020/05/25 掲載
コロナ禍で加速する「組織と価値観の解体」、なぜブロックチェーンが鍵を握るのか

前編、中編はこちら(※この記事は後編です)
ブロックチェーンは本当に広がるのか?

そして、小林氏は、この新しいトレンドを構成する中核テクノロジーとして「ブロックチェーン」を挙げる。ただし、現時点でブロックチェーンは、社会を一変するほどのアプリケーションが生まれているようには見えない。小林氏は、どう見ているのだろうか。
「1994年12月にWIRED JAPANを立ち上げたとき、外国人記者クラブで記者発表をしました。そのとき、日本の新聞社の記者の方から『インターネットは米国では流行っているが日本では流行るとは思えない。リスクを感じないのか』という質問を受けました。そのときの状況と似ていると思います」(小林氏)
1993年にWebブラウザのMosaic(モザイク)が登場するまでは、インターネット上にはニュースグループやFTPなどのバラバラなアプリケーションが存在していた。それが、Mosaicの登場によって、それまでインターネットに関心のなかった層にまで一気に広まった。
「たとえば、『CryptoKitties(クリプトキティーズ)』というブロックチェーン上で稼働するゲームがあります。それをやりたくてウォレットを用意し、イーサリアム (ETH)を購入して……とやっていると、苦労してダイヤルアップしてインターネットにつないで……とやっていた、あの頃の状況に近いものを感じます(笑)」(小林氏)
期待されるブロックチェーンにおける“Mosaic”の登場
ブロックチェーンを取り巻く状況について、小林氏は「今はまだプロトコルレイヤーで、超オタクな世界です」と説明する。インターネットでいえば、TCP/IPやHTTPのレイヤーで盛り上がっている状態で、もっと使いやすい分散型技術やサービスが登場する可能性はあると指摘する。「Mosaicが出てきたとき、『何だコレは! 今までの苦労は何だったんだ』となりました。当時はWi-Fiなんて夢物語でしたし、3Dプリンタも、昔、WIRED JAPANで取り上げたときは、何億円もする世界で数台しかないものでした。GPSを利用したナビ製品はまったく使い物になりませんでした。新しいものが出てきたとき、それを否定するのは簡単です。しかし、いまは3Dプリンタは数万円で買えますし、初期には「使えない」と思われたGPSはスマホのアプリに実装され日常でないと困る存在になっています」(小林氏)
現在、世界中でブロックチェーンのさまざまなプロトコルが開発されている。それがいずれ相互運用可能となったり、もしくはMosaicのようなエンド・ユーザー向けに洗練されたアプリケーションが開発される可能性は十分にある。
「あるいは、革新的なハードウェアが登場する可能性もあります。たとえば、ブロックチェーンを利用した『XPhone』というスマートフォンがあります。HTCからもブロックチェーン対応の『Exodus1』といスマートフォンが出ています。このようなエンドユーザーが恩恵を受けられるマイルストーンが、いずれは登場するのではないかと思います」(小林氏)
企業、自治体、価値観が解体されたあとに何が生まれるのか
『After GAFA 分散化する世界の未来地図(KADOKAWA刊)』で、小林氏はこれから「ビッグアンバンドル(大いなる解体)」が起きると指摘している。会社や自治体といった、従来は当たり前に存在すると思われていた組織が解体され、新たな融合が始まるというのだ。「これからは、民間が入らないとやっていけない自治体が出てきます。たとえば、公園のイスが壊れたら自分達で直す、交通インフラはシェアサービスに任せるといった、新しいコミュニティのようなものが必要になるでしょう。多くの会社も、いま、黒字リストラをやっています。内部留保があるうちに、給与が高い人達に辞めてもらおうとしているのです。新入社員を採用し、各部門を経験させて、ゼネラリストを育成するといった従来の仕組みの賞味期間はもう過ぎているのです」(小林氏)
確かに、一部の企業で副業を認める動きも起きている。1つの会社に勤め上げるという時代は終わり、複数の会社に同時に属して収入を得る。もしくは、会社に所属しながら、個人でビジネスをするといったパラレルキャリアの世界が、夢物語ではなくなりつつある。
「『アンバンドル』というのは、これまで当たり前だったパッケージが分解されていくイメージです。たとえば、今後は1人の社員が複数の会社と契約することもありうると思います。そこでは、企業とは何か、自治体と何かといった本質的な問題が問われることになるのです」(小林氏)
コロナ禍がこうした本質的な問題を社会や企業に問うことは明白だろう。
【次ページ】「資本主義的な価値観」が分解された先にある世界とは
関連コンテンツ
PR
PR
PR