- 会員限定
- 2015/10/26 掲載
「案件の同時処理が得意です」という人の実務能力は疑わしい
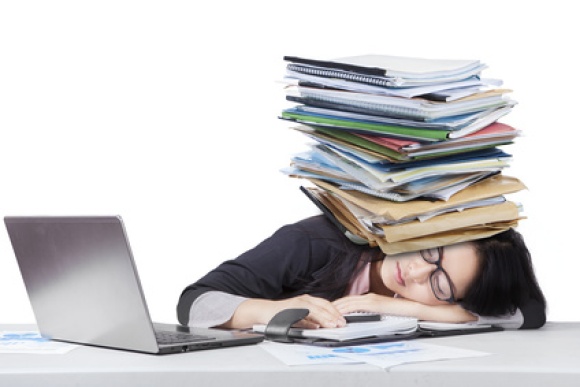
人は複数のことに集中することはできない
「マルチタスクをこなす学生には、何か特異な能力があるに違いないと考えていました」と、調査を主導した教授は言う。「しかし、彼らはあちこち関係のないことに気が向いてしまうのです」。結局、彼らはすべての評価基準で成績が下回ったのだ。
「マルチタスクは効率的」というのは嘘である。
にもかかわらず、ほとんどすべての人が、それを効率的な仕事のやり方だと考えている。600万以上のウェブページがその方法についての回答を提供し、転職サイトでは、「マルチタスクをこなすこと」を雇用主が求めるスキルとして、また求職者が自分の強みとして挙げている。
だが実は、マルチタスクは効率的でも効果的でもない。成果が問題になる世界では役に立たないのだ。
一度に二つ以上のことをこなす人という概念は、1920年代から心理学者によって研究されてきたが、「マルチタスキング」という言葉は1960年代になって初めて登場した。当初、それは人間ではなくコンピュータに対して用いられたものだった。多くのタスクを驚くべき速さでこなすコンピュータの能力を表現するために、新しい言葉が必要だったのだ。
しかし、これは誤解を招く表現だった。というのもコンピュータですら、厳密には一度に一つのことしか処理できないからだ。
コンピュータが「マルチタスク」を行う場合、スイッチを切り替え、順番に注意を向けて複数のタスクを完了させる。その切り替えの速度があまりに速いため、まるですべてが同時に処理されているかのように錯覚させられるのだ。だから、コンピュータを人になぞらえると誤解をまねくことになる。
実際には、人は歩くことと話すこと、あるいはガムを噛むことと地図を見ることのように、一度に二つかそれ以上のことができる。だが、コンピュータと同じで、同時に二つのことに集中することはできない。人がこれをしようとすると注意が散漫になり、重大な結果を引き起こす。
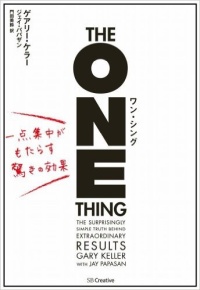
不思議なことだが、いつからか現代人はマルチタスクをこなすことが当たり前になってしまった。私たちはそれができると信じ、だからそうすべきだと考える。
子どもたちはケータイでメールしたり、音楽を聞いたり、テレビを観たりしながら勉強をする。大人は電話で話したり、ものを食べたり、化粧をしたり、ひげ剃りすらしながら車を運転する。時間がないからではない。限られた時間に多くのことをしなければならないと感じているのだ。
【次ページ】 マルチタスク思考が損である理由
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR


