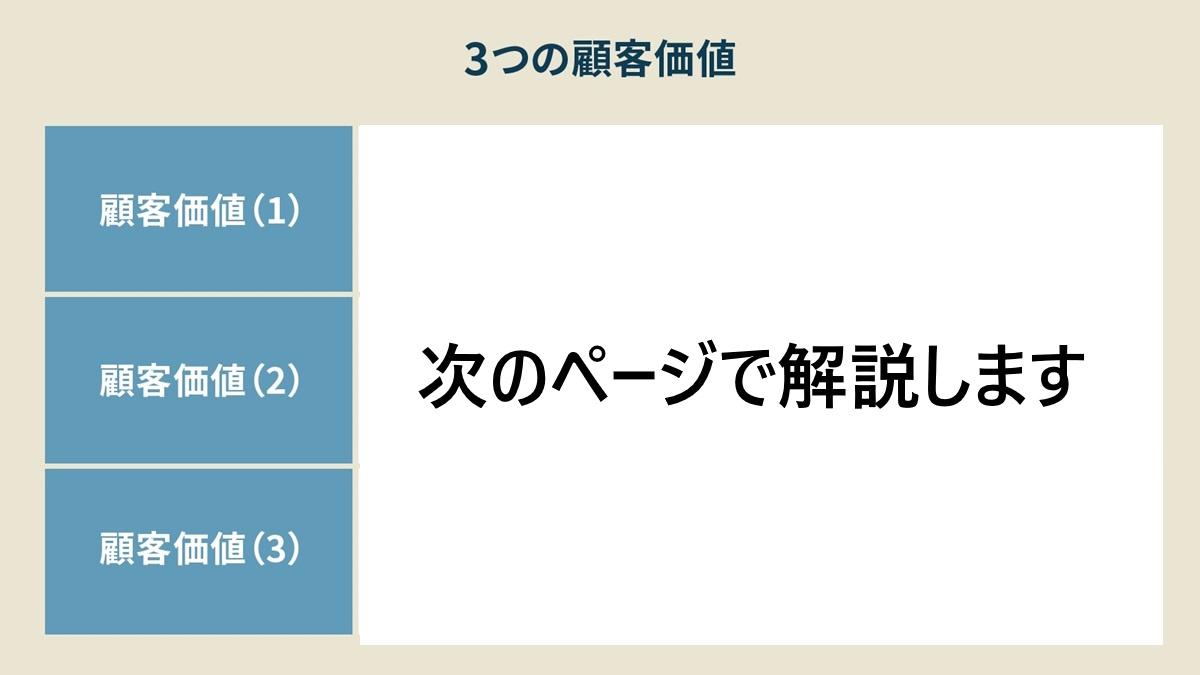- 会員限定
- 2025/02/03 掲載
若手からのタイパ提案が「ただの手抜き…」、でも会社にとって「大チャンス」のワケ
「効率化」と「手抜き」は何が違う?
まず、効率化や生産性を高めるとはどういうことか。それは時間や手間を減らしても「顧客価値」が変わらない、または向上することです。この視点がなければ、効率化はただの手抜きになってしまいます。たとえばある若手社員が「会議の時間を短縮するために、毎週のミーティングを隔週にする」という提案をしたとします。会議の頻度が減ることで、情報共有のタイミングが遅れ、結果的に業務全体の効率が低下するリスクも考えられます。
ただ、会議の時間を削減することで、他の業務に充てる時間が増え、生産性が向上するかもしれません。
ここで重要なのが、顧客価値がどう変わるかを一緒に考えることです。効率化の提案が本当に効果的かどうかを判断するためには、その提案が「顧客価値」にどう影響するかを慎重に評価する必要があるのです。
よくある「営業回り廃止」の提案
具体的な事例で見てみましょう。若手社員からの“業務の効率化”の提案でよくあるのが、「営業回りは非効率だから電話・メールにしましょう」というものです。たとえば、ある企業では、営業担当者が定期的に顧客のオフィスを訪問することが当たり前になっていました。交通費や移動時間のコストが増大するとともに、生産性が低下していることが問題視されました。
そこで、若手社員から「顧客訪問を減らし、代わりにビデオ会議を活用する」という提案がありました。この提案が実行されることで、顧客とのコミュニケーションといった価値を維持しつつ、移動にかかるコストや時間を削減することができ、生産性が向上しました。
では具体的に、判断基準となる顧客価値とはどのようなものでしょうか。本稿では3点を紹介します。
【次ページ】でも「ただの手抜き」も「大チャンス」となるワケ
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR