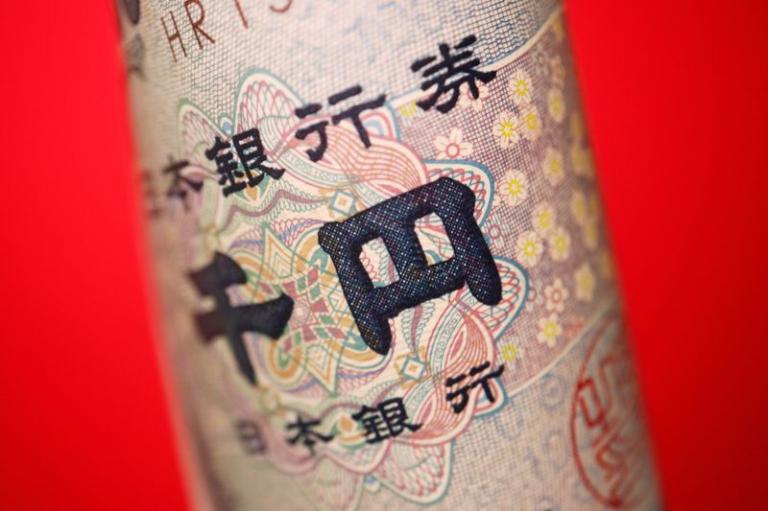- 2025/02/18 掲載
アングル:長期金利上昇に勢い、年度内1.5%意識 上がる投資家目線
[東京 18日 ロイター] - 国内の金利が市場参加者の想定を上回る速さで上昇している。18日の円債市場で長期金利の指標となる新発10年国債利回りは1.4%台に上昇(価格は下落)。わずか1週間余りで台替わりとなった。年度末を控えていることもあり、投資家は様子見姿勢に徹しており、すでに年度内1.5%を意識した声も広がりつつある。
<「意味のある節目ではない」>
この日の金利上昇の直接的なきっかけは、財務省が実施した20年利付国債入札が弱い結果に終わったことだ。事前には、利回り水準の高さを背景に消化に十分な投資家需要が集まるとの見立てが大半だった。このため、予想外の入札結果が伝わった後場入り後に一気に債券売りが膨らんだ。
節目の1.4%をつけた後も投資家による押し目買いの動きは乏しく、長期金利は09年11月以来、15年3カ月ぶり高水準となる1.43%まで短時間で上昇した。
2024年は長期金利1.1%の水準が、投資家の買いが入ってくる「壁」として意識され、幾度となく跳ね返されてきた経緯がある。それが1月の日銀の金融政策決定会合を終えて以降、日に日に地合いが悪化してきた。
岡三証券の長谷川直也チーフ債券ストラテジストは「1.4%は節目ではあるものの特別な意味はない。1.2%と1.3%もそうだったが、1.4%をつけたからといって市場に達成感はない」と話す。
<落ちるナイフ>
1月の利上げ後も金利上昇が勢いを増しているのは、日銀からの情報発信も一因だ。会合後の植田和男総裁、氷見野良三副総裁、田村直樹審議委員による発言内容がいずれも「タカ派的」と受け止められた。
利上げのペースや到達点を巡り、市場参加者の想定がじりじり上方修正されたのに伴い、円金利は日銀の政策を反映しやすい中期ゾーン主導で速いペースで上昇した。
「足もとの金利上昇ペースが速いこともあって投資家のスタンスが慎重化している」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の鶴田啓介シニア債券ストラテジスト)といい、落ちるナイフに手出しできない状況となっているようだ。
年度末が近づく中、債券の買い手がいない需給環境の悪さを指摘する声もある。銀行勢が主要な投資家層である5年債は、24年度初めの利回りが0.3%台半ばだったが、足もとでは16年超ぶり高水準の1.1%手前まで上昇している。
関西みらい銀行の石田武ストラテジストは「金利上昇でかなりの評価損を抱えるところがほとんどだと思う。年度末を前にどの投資家もリスク許容度が低下しており、多少金利が上がっても投資しようとはなりづらい」と述べ、銀行勢が買いに動く目線は切り上がっているとの見方を示す。
<年度内1.5%視野、「正常化の痛み」>
先行きに目を転じると、物価や賃金に関するデータの発表や日銀当局者からの情報発信など、市場に日銀の利上げ継続を意識させやすいイベントがいくつも控えている。当面は、金利に上振れ圧力がかかりやすい展開が想定される。
今週だけでも、19日に日銀の高田創審議委員の講演・会見、21日に1月の全国消費者物価指数(CPI)の発表があり、金利が上振れで反応するリスクが警戒されている。来月5日には日銀の内田真一副総裁の発言機会があり、同14日には春闘の第1回回答集計結果の発表もある。
年度末を前に投資家の慎重姿勢が続くとみられる中、市場では長期金利が次の節目の1.5%に向けて一段と上昇する可能性を見込む声が多い。
岡三の長谷川氏は、1.5%の水準に特に意味はないとした上で、3月末までに1.5%をつけることは十分あり得ると予想する。「金融政策が正常化され、(買い手としての)日銀のプレゼンスが縮小していることも背景だが、金利のある世界に戻るとはこういうことだ。いわば『正常化の痛み』といえる」と指摘した。
(植竹知子 編集:平田紀之、橋本浩)
PR
PR
PR