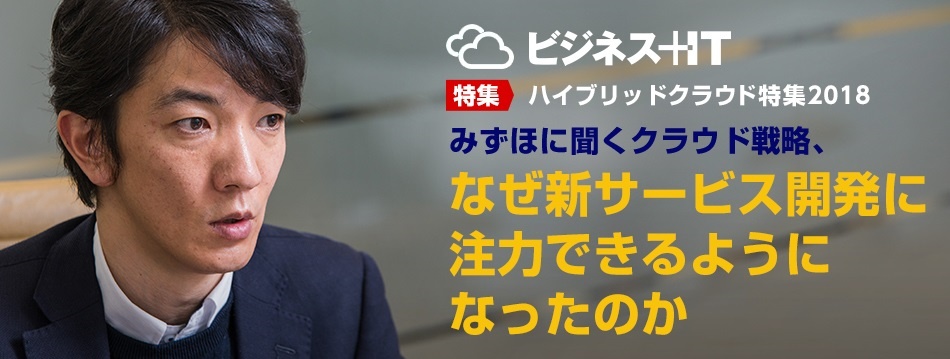- ありがとうございます!
- いいね!した記事一覧をみる
みずほに聞くクラウド戦略、なぜ新サービス開発に注力できるようになったのか
2014年7月、Amazon Web Services(AWS)が開催したイベントで、1つの注目すべきセッションが開催された。金融業界で初となるネットバンクによるAWS導入の詳細を説明したセッションだ。そのプロジェクトの中心人物であり、セッションの登壇者でもあった大久保光伸氏は、3年後の現在、みずほフィナンシャルグループで、デジタル戦略を推進するキーパーソンとして活躍している。みずほのクラウド戦略とは何か。企業がクラウド化を推進するうえで必要なことは何か。話を聞いた。
デジタルイノベーション部シニアデジタルストラテジスト
Blue Lab最高技術責任者(CTO)
約17年間、規制当局のガイドラインに準拠した金融機関システムの企画・開発業務と、先端技術の活用調査・検討業務に従事。前職の金融機関では、日本初となるパブリッククラウドの導入をリードし、国内外で事例を公開。クラウドエコシステムの構築に貢献。現在、みずほフィナンシャルグループにてデジタル戦略を担当しAPI活用によるオープンイノベーションを推進。一方では、一般社団法人 金融革新同友会FINOVATORSのFounder兼CTOとして、FinTechスタートアップへのメンタリングやパブリックセクターへの提言、海外FinTech業界団体との連携等により金融イノベーションのエコシステム形成に携わる。2016年11月から一般社団法人 Fintech協会のアドバイザリーボードに就任。2017年7月よりBlue LabのCTO(最高技術責任者)を兼務。
金融機関にもクラウド化の波が……
──最初に大久保さんとクラウドとの関わりについて教えてください。大久保氏:私がクラウドに関わったのは、今から約10年前です。当時、システムインテグレーター(SI)企業で、金融機関向けにネットバンクのコンサルタントとして仮想化技術の研究開発を担当していました。そこで、従来はハードウェアで担保していたセキュリティをソフトウェアで実装しても十分担保できることを確認したのです。
EucalyptusやXen、VMware、KVM、Hyper-Vなどのクラウド基盤を支える仮想化技術について、ありとあらゆるテストケースを作成し、負荷テストツールを用いて徹底的に検証しました。
──最近のクラウドを取り巻く環境は、当時と比較して変化がありますか。
大久保氏:ユーザー企業においてパブリッククラウド導入の流れが本格化しました。契機は、AWSが東日本にリージョンを開設したことです。そして、その直後に発生した東日本大震災の影響が大きいと思います。
当時、多くのデータセンターが被害を受け、各社が対応に奔走していたとき、AWSは困っている企業にAmazon S3(Simple Storage Service)を解放しました。その結果、「自前のデータセンターとパブリッククラウドを比較した場合、どちらが安全なのか」という議論が起きるようになったのです。
その後、BCP(Business Continuity Planning)の観点からもパブリッククラウドが有効と考えられるようになり、三井物産や東急ハンズのように、システムをAWSに移行する企業も登場して来ました。
ただし、当時クラウド化を推進したのは、ITドリブンな先進的な企業に限定されていたことも事実です。しかし最近は、シェアリングエコノミーのような「所有から利用へ」といった流れがあります。
サブスクリプション型のビジネスも登場し、「使ったぶんだけ支払う」という考え方も認知されてきました。クラウドを取り巻く環境は、かなり変わってきたと感じます。
・金融機関が評価するクラウドのメリットは
・クラウド推進の“ストッパー”を懐柔する秘訣
・みずほ銀行のクラウド活用戦略とは……
今すぐビジネス+IT会員に
ご登録ください。
すべて無料!今日から使える、
仕事に役立つ情報満載!
-
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
-
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
-
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
-
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!