- 会員限定
- 2020/09/24 掲載
日生やあいおいニッセイ同和らが激論、「ニューノーマル」の保険業界はどう変わるか

コロナがもたらした保険業界へのインパクトは?

保険業界では、コロナ禍で対面での営業や取引、契約が困難になり、オンラインでの非対面取引が注目されている。「ニューノーマル」を踏まえ、今後、保険業界ではどのようにビジネスを展開していけばいいのだろうか。大手保険会社の企画・開発担当者やInsurTechを推進する担当者たちの見解を紹介する。
まず、justInCaseの畑氏は「コロナ対応でオンライン化が一気に進んだことで、保険代理店も『勝ち組』『負け組』の評価が出てくる。現在の立ち位置はそのまま続くのか、それとも変化するのか。今後、どのような要素が勝ち負けを決めるのか」という質問を紹介した。
𡈽川氏は、いわゆる「ハイパフォーマー」と呼ばれる、顧客グリップがきっちりできている募集人については、あまり影響を受けていないようだと語る。
同氏が注目しているのは、2020年に就職活動している学生だ。「人生最大の一大事をオンラインで切り抜けて2021年に入社してくる。これはとてもすごいこと」(𡈽川氏)と分析する。以降の世代では「なぜ対面で会わなければならないのか」と、リアルな面談をすることにあまり価値を感じない人も出てくるだろうと指摘した。今後は「どこにいるか」といった物理的な場所は関係なくなるというのだ。

代表理事の𡈽川 尚己氏
また、𡈽川氏は「今は過渡期であるが、5年後、10年後を考えると、人が介在する前提ではオンラインコミュニケーションスキルが高い保険募集人が生き残る」と予測。「インシュアテックが“全部持って行く”のではという不安があると思うが、募集人がオンラインで空間を超える可能性をふまえると、インシュアテックもサービス自体も考え直していく必要がある」と指摘した。
オンライン化は生命保険の営業職員の脅威になるのか?
次に畑氏は、関氏に対して「コロナの影響でインターネットでの保険申し込みが最も多くなっているが、日本生命に限らず生命保険の営業職員は相当な危機感を抱いているのではないか」と質問した。関氏は「非常に難しい質問」と前置きした上で、「オンラインか、オフラインかはあくまで手段であり、重要なのは生命保険の加入につながるバリュー(価値)をいかに出せるかにある。たとえば、オンライン専業銀行について本社の場所を知らなくても便利なら利用するであろうし、お客さまの“生活圏内”にあることが価値になる」と説明した。
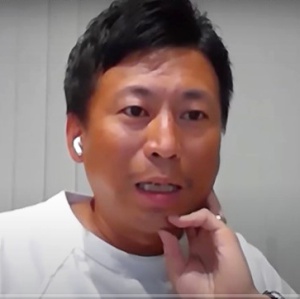
課長 関 正之氏
関氏によると、日本生命では現在、オフラインの販売活動がメインになっており、オンラインでの販売は“一部”という状況だ。しかし、「今後状況が変化して保険の加入手続きまでをオンラインで完了できるようになると、当然ながら選択肢が広がるので、顧客の要望に見合った価値を提供できる接点を持ったチャネルが選ばれることになっていく」と語った。
また、あらゆる業態でオンライン化が急速に進む可能性があると指摘した。「世の中全体のオンライン化が進む中で、対面チャネルの難しさは、これまでも多く論じられてきた。つまり、新型コロナの影響でゼロからスタートということではなく、コロナ禍でさらに加速するという認識だ」(関氏)
その上で「外部の知見やソリューションをどのように使えば、市場に見合ったものを出していけるか」という質問を例に出し、「これから加速度的に進んでいくオンライン化に対応できるかどうかが今後の企業競争力の差になるので、その点は見誤らないようにすべき」と説明した。
コロナの影響で新しく動き出した点とは?
続いて畑氏は、あいおいニッセイ同和損害保険の若狭氏に対する質問として「地方創生やMaaS(Mobility as a service)への取り組みがコロナ禍で止まっていると思うが、逆にコロナによって進み出したことはあるのか」と投げかけた。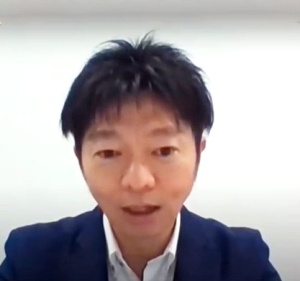
室長(当時) 若狭 弘幸氏
若狭氏は「𡈽川氏が言うように対面での打ち合わせがオンラインに移行したことで、気軽なタイミングで打ち合わせができるようになったこと」を挙げる。
若狭氏は、あいおいニッセイ同和損保と香川大学が共同実施しているMaaSに関する特別共同研究を例に挙げた。「現地に行くとなると片道で半日かかるが、オンラインであればすぐにでも打ち合わせができる。その意味では進んでいるところも多い」ということだ。
また若狭氏は、コロナによって変わった点の1つとして、新しいビジネスが出てきていることを挙げた。コロナ禍では物流は止まるどころか、逆に回らないほどになっており、タクシー運転手が買い物などを代行する「救援タクシー」の取り組みを延長するという報道も出ている。
このことから、「MaaS領域だけを見ても新しいビジネスが登場しているし、止まらない部分と止まっている部分の両方がある」と見ているという。
保険業界のスタートアップが出てこない理由とは?
続いて、畑氏は「インシュアテックを含め日本のスタートアップがそれほど多く出てきていない理由は何か」という質問を紹介した。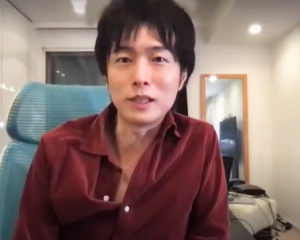
津崎 桂一氏
その一方で、環境の変化への対応が遅いという傾向もあるとした。たとえば、コンシューマー向けでは“VTuberが来る”など分かりやすい波があるが、保険分野は目に見えるインパクトも薄い。「今後はマーケットの大きさに見合った“刺せるポイント”が多く表面化すると考えられるため、スターアップの参入も増えるのではないか」と予測した。
【次ページ】「営業担当者の余剰人員問題」に取り組むには
PR
PR
PR


