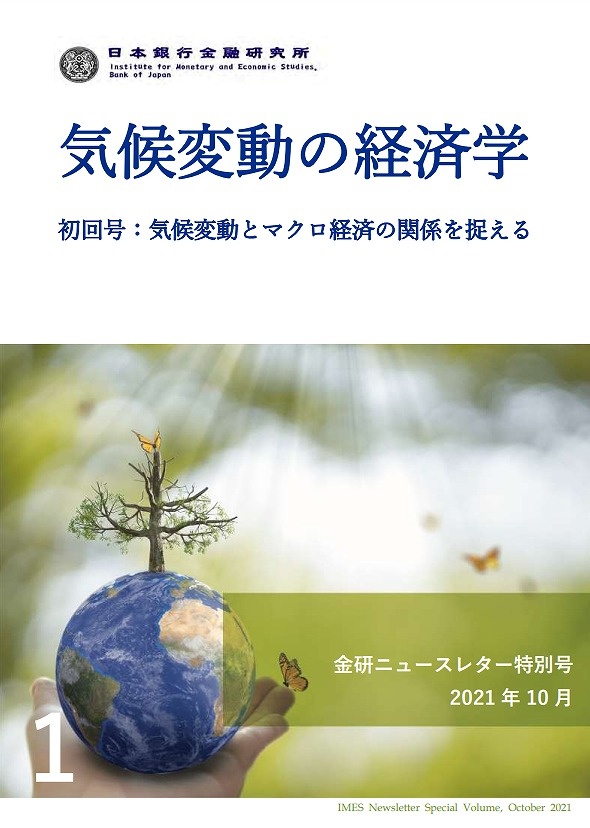- 会員限定
- 2022/02/07 掲載
経済学で気候変動に挑む方法とは? 日銀がレポートを出した理由

なぜ日銀は「気候変動」のレポートを出したのか?
──最近、日本銀行金融研究所が「気候変動の経済学」に関する調査を発表しました。その狙いは何でしょうか。副島 豊氏(以下、副島氏):なぜ、気候変動問題に対して経済学のアプローチで取り組むのか。目的は大きく2点です。1つ目の理由は、気候変動と経済の間にある複雑で不確実性が高い相互依存性について、定性的・定量的なモデル化を試みるためです。2つ目は、こうした定量分析に基づいて気候変動問題に対する適切な政策対応を検討する材料を得るためです。今回の調査は、手始めに気候変動問題に関する経済学の主要な研究を調査して公表しました。
日本銀行はこの2021年7月に気候変動ヘの取り組み方針を公式に発表しました。そこで日本銀行の取り組みの1つとして調査研究を挙げています。
日本銀行 金融研究所は、日本銀行の研究部門として経済理論、ファイナンス、法律、IT、会計、金融・貨幣史など各分野を研究しています。時代を先取りして行われているこれらの研究は、多くの場合5~10年後に実務で大きな意味を持つようになります。
たとえば1990年代に暗号技術を研究した際には「なぜ日銀が暗号を?」と思う人も少なくありませんでした。しかし現在、暗号技術は金融に欠かせない要素技術です。金融システムの安定性に関する研究は、金融市場の発展とリスク管理の高度化が進んだ90年代には個々の金融機関の健全性に焦点がありましたが、金融危機の後ではシステムとしての振る舞いを検証することの重要性が強く意識されるようになりました。
現在、気候変動問題は世界の大きなテーマです。政治やビジネス、そして金融の側面から、どのような取り組みが必要なのかを知る必要があります。判断の基礎となるのは定量的な現状認識と問題の全体を見通せる理論。定性的な議論や感情論では良い意思決定はできません。この点、経済学のものごとの見方と分析手法は有益です。理論に基づくモデルを作り、研究することで、はじめて気候変動への定量的な処方せんを知ることができるのです。
気候変動対策は「割に合う」のか
──気候変動と経済活動のモデルに関する議論は、年を追うごとに変化しています。以前は「気候変動対策にコストを投入するのは経済的に割に合わない」という意見もあったのですが、最新の精緻なモデルに基づく議論では「気候変動対策にはコストを支払うべきである」というトーンに変わっています。副島氏:複雑な要因が絡まる気候変動問題の「経済モデル化」は簡単ではありません。コアな土台作りから始まり、段階を踏んで発展し続けています。そこで今回の調査では最も基礎的なDICE(Dynamic Integrated Climate-Economy)モデルを最初に取り上げています。
モデル化して処方箋を知るといっても、一回結論を出しておしまいになるわけではありません。気候変動や経済に関するデータは日々更新されているため、モデルによる予測結果は最近になるほど精度が向上します。
モデルも精緻なものに進化し続けています。したがって継続的な研究と議論が必要です。ある時点の予測が数年後に「見積もりが甘かった」と訂正されるかもしれないし、逆に「過剰な見積もりだった」という結論になるかもしれません。
マクロ経済理論は、動学的分析に適するモデルを持っています。1980年代に、ミクロ経済学的基礎付けに基づく動学的確率的一般均衡モデル(Dynamic Stochastic General Equilibrium Models; DSGEモデル)が発展しました。これは長期的な分析に向くものです。このモデルは、気候変動問題の対応に今どれだけコストを支払うと、将来どれだけ被害を抑えられるか、そのトレードオフを定量的に認識できます。
DICEモデルの経済理論上の基本も、このDSGEモデルです。やや癖や注意点はあるのですが、動学的な分析により「気候変動による未来の被害を減らすために、今どれだけコストを支払って努力すればよいのか」、「両者のバランスをとった最適な対応の進め方は、どのような時間経路上のパスを辿るか」を定量的に導出できます。
【次ページ】DICEモデルを詳説
PR
PR
PR