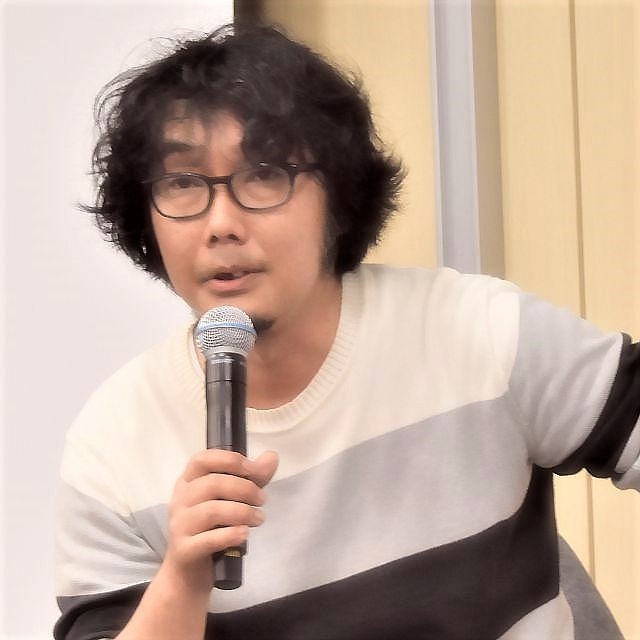- 会員限定
- 2019/09/30 掲載
EUで誕生、「価値が減る通貨」と「プライバシーデザイナー」の意義とは?
武邑光裕×若林恵×林尚見×坂井豊貴
前編はこちら(※この記事は後編です)
ブロックチェーンはどちら側に立つテクノロジーか
若林氏:先程、中国では規制によって安全度が上がることで国民の幸福度が上がっているのではという仮説が紹介されました。そして、EUではその中国から「ブロックチェーンとGDPRの共生」を学ぼうとしているという話もありました。自由と安全、利便の対立があったとして、特に若い世代が、安全度が低いなら「自由は面倒くさい」と感じ始めているところがありそうです。そういう中で、ブロックチェーンのコミュニティというのは「自由が大事」という理解でいいのでしょうか。
坂井氏:ブロックチェーンといってもさまざまで、ここではいわゆる仮想通貨、特にビットコインについて話したいと思いますが、やはり自由だと思います。ビットコインが出たのは2009年ですが、ビットコインのような発想は、実はもう1980年代には存在するのですよね。このとき、もうこれからお金のやりとりは電子上でなされるということを予見した人が何人かいました。
たとえばデビッドショーン(David Chaum)という計算機科学者が「電子上でお金をやりとりするようになると、その管理者は誰が何にお金を使っているか、日時まで全部正確に分かる。これはプライバシーの大変な侵害であって、われわれの自由を今後根本的に脅かすことになるだろう」と考えていました。それで彼は90年代にECashというビットコインの走りのようなものを生み出します。
でもまだ時代がそこまで追いついていなかった。インターネットもそんなに普及していませんでした。そのようなプロジェクトがいくつかあって、遂に2009年にビットコインが出た。
最初ビットコインを熱心に支持した人たちは、リバタリアン(自由至上主義)が非常に多かったといっていいと思います。「国家にお金の管理は任せられない、われわれが自分たちで運営しよう」と。そういう意味ではいわゆる「強い個人」が多かったのです。
貨幣の常識を覆す?「減価する貨幣」の台頭
武邑氏:EUでの1つの潮流としては、ビットコインの前段階に、互換通貨とか地域通貨と言われている、特にシルビオ・ゲゼルの「自由貨幣」の発想がありました。これは別名、“減価する貨幣”ともいって、あらゆる自然物はすべて価値が減少していくのに、お金だけが腐らないというのは違うのではないか、これを減価させなければならないとゲゼルは考えたんですね。この考え方を受けて登場したのがドイツのバイエルンで流通しているキームガウアー、スイスで流通しているヴィアといった地域通貨で、この2つは大成功しています。減価がどこで発生するかというと、2%ぐらいの一種の通貨税のようなものを3カ月ごとに払わなければならない。
だから、持ち主にはできるだけ早く使おうという意識が働く。流通速度が非常に上がるため、デフレーションの対策に効果的だったり、コミュニティベースでお金を作るという原型がここにあるんですが、これを今ブロックチェーンでやろうとしているんです。
坂井氏:地域通貨にして減価通貨ですか。要するに、使わなかったら通貨の市場コストがだんだんかかっていくと。
武邑氏:そうです。1万円を3カ月以内に使わないと、税金を払わなければいけないからみんな早く使う。貯蓄は人間的ではないという考え方に立っているんですね。
坂井氏:すごいですね。面白いと思うのですが、ものすごく抵抗があります(笑)。一応、経済学者なので、貨幣とは何かという授業をするんですが、そこでは「腐らない財が貨幣たり得る」というのが大前提です。
武邑氏:でもそれはフィアット(Fiat、法定通貨)ですよね。
坂井氏:フィアットじゃなくても、世の中でこれまで貨幣として流通してきたものというものは、恐らく全部腐らないものばかりだったはずなのです。だから、減価する貨幣というのは面白いのかもしれないですけど、生理的には気持ちが悪いですね。この気持ち悪さが何に基づくのかというと、お金の重要な機能が「価値の保存」だと私は考えているからです。
たとえば僕が漁師だとしましょう。今年は大漁だった。でも、来年は魚が獲れない。来年に今年の魚が食べられればいいけど腐ってしまう。腐るものは価値の保存ができないから腐らないお金に換える。
腐る魚は腐らないお金になって、それを来年自分の食料と交換すればいい。これってすごい発明ですよ。にもかかわらずゲゼルの自由通貨は価値の保存という貨幣の役割を部分的に放棄している。悪いとはいわないですけど、ラディカルだなと思います。
【次ページ】企業と個人の間をとりもつプライバシーデザイナーの出現
関連コンテンツ
PR
PR
PR