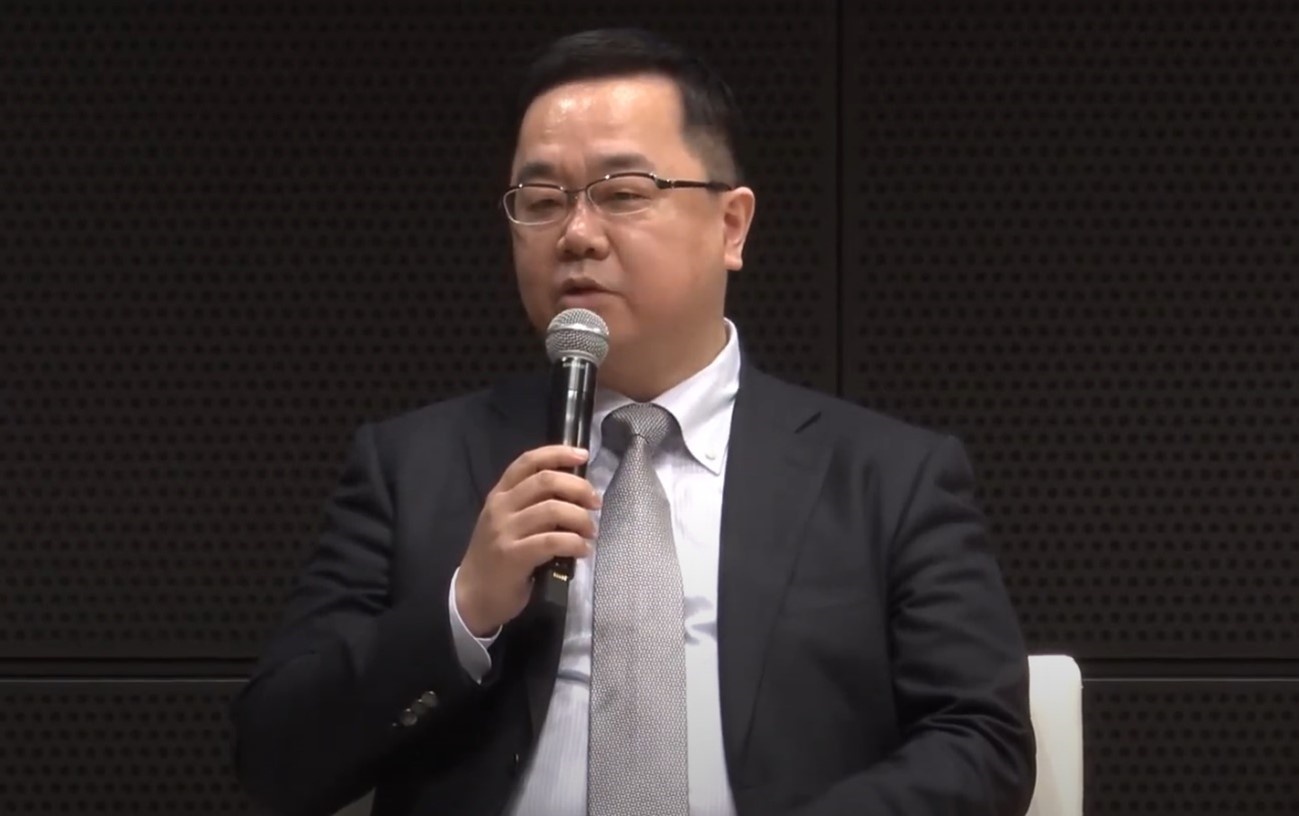- 会員限定
- 2021/08/04 掲載
「NFTはバブル」「DeFiは"予見済"」、金融庁やSBIらが語る暗号資産市場の行くすえ

暗号資産のバブルが起こった理由
日本経済新聞社でフィンテックエディターを務める関口 慶太氏は、議論の最初にビットコインの価格の2017年以降のチャートを示した。2017年初めは1,000ドルの水準だったものが1年で約20倍の2万ドルまで伸び、「この時、『仮想通貨バブル』だと言われていた」と振り返った。その後バブルが崩壊して冬の時代を迎えたが、2020年、バブル当時の2万ドルを易々と突破し、一時(2021年4月)は6万ドルを超える水準に達した。「2万ドルでバブルと言っていたのに、何が起きたのか」と関口氏はパネラーに問いかけた。
SBIセキュリティ・ソリューションズ、SBIデジタルアセットホールディングスの2社の代表取締役を務めるフェルナンド・ルイス・バスケス・カオ氏は、「ここ数カ月の上昇相場の勢いもあって個人投資家の動きが非常に活性化している」としつつも、「2017年のバブルに比べると冷静さを保っているのではないか」という見解を示した。
「ハッキングによる流出リスクや所得への課税といった知識を身につけて、バブル後に出てきたステーキング(対象の暗号資産の保有により対価がもらえる仕組み)や、先物などの金融商品を巧みに組み合わせた長期保有志向の個人投資家が多いと思われます」(フェルナンド氏)
さらに、2017年の相場が個人投資家主導だったのに対して、今回の上昇相場は事業法人を含めた機関投資家が刺激していること、それも、ペイパルやツイッターなどの先進的なテック企業だけでなく、フィデリティなどの伝統ある大手金融機関も暗号資産を購入したり、事業展開を表明していることを指摘し、「今回の上昇相場の底支えしている」と話した。
また、暗号資産取引所運営のHuobi Japan代表取締役社長を務める陳 海騰氏も、2017年の上昇相場と比較して今回は海外を中心に機関投資家や大企業が参入してきたことに同意しつつ、「日本のマーケットも変わった」と話す。
「2017年のときはベンチャーがメインでしたが、最近はヤフー、ライン、マネックス証券など大手企業も入ってきています。プレイヤーが様変わりしました。2017年には流出事件や暴落などがあり賛否両論ありましたが、その後、法律を含め環境が整備されてきています。また、暗号資産が『デジタルゴールド』として認知されつつあるのも変化の1つ。個人投資家でも、株や債券、不動産などと並んで暗号資産に投資する人が増えています」(陳氏)
ブロックチェーン技術を土台に生まれる新ビジネス
現在は、暗号資産の売買に関わるビジネスだけでなく、そこで使われるブロックチェーン技術を土台にした新しいビジネスも生まれてきている。モデレーターの関口氏は「そこにチャレンジしているのがBOOSTRYの佐々木 俊典さん」と紹介し、同社の取り組みについて聞いた。BOOSTRYは、野村ホールディングスと野村総合研究所で設立した合弁会社であり、SBIホールディングスも資本参画している。BOOSTRYのCEOである佐々木氏は、「当初は仮想通貨と呼ばれていたことからも通貨のような見立てが主流だったが、法律で暗号資産に名称が変わり資産性が着目されるようになった」と話す。
「当社で取り組んでいるのはセキュリティトークンと呼ばれるもの。まさに資産性があり、人の間で移転しやすくしたり自動化できたりするブロックチェーンを使うメリットのあるものです」(佐々木氏)
BOOSTRYでは、デジタルアセット債のほか、証券化商品と呼ばれる、従来個人には馴染みのないもの有価証券のほか、証券ではないデジタル会員権なども取り扱っている。「将来的には未上場株にも発展性があるほか、ノンファンジブル・トークン(NFT)のような『デジタルの権利』と言えるものまで含めて広がっていくと考えており、そうしたエコシステムが広がることがポテンシャルになっている」と佐々木氏は話す。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所の弁護士である河合氏も、「ブロックチェーン技術の発展もあり、使われる場面が増えてきている」と指摘する。
「つい先日もデジタルアートのNFTを出したいアーティストと、トークン化するブロックチェーン技術企業との間の著作権に関する契約を作る機会がありました。そういう相談や仕事は非常に増えています」(河合氏)
暗号資産そのものについてもビジネスが変わってきており、単に売買だけでなく、レンディング(貸出)/ボローイング(借入) が行われたり、暗号資産を預けることによって新たな暗号資産を得るなど。長期保有による運用を意味するステーキングというビジネスも出てきている。
資産性のあるものとは別に、決済性のあるものへのビジネスも進んでいる。たとえばステーブルコインや、中央銀行デジタル通過(CBDC)などがそれだ。「ただし、ステーブルコインについて、日本では法制度上の位置づけがまだ明確ではないため、今ひとつ踏み出せていないというのが現状」だと河合氏は話す。
「それ以外にも、たとえば国際貿易における船荷証券のように、これまで紙を使ってきたが取り扱いが煩雑なものをデジタル化してブロックチェーンに乗せようとする動きがあります。今までよりも産業界で使われる裾野がはるかに広がっているというのが今の私の実感です」(河合氏)
【次ページ】NFTはバブルなのか?
PR
PR
PR